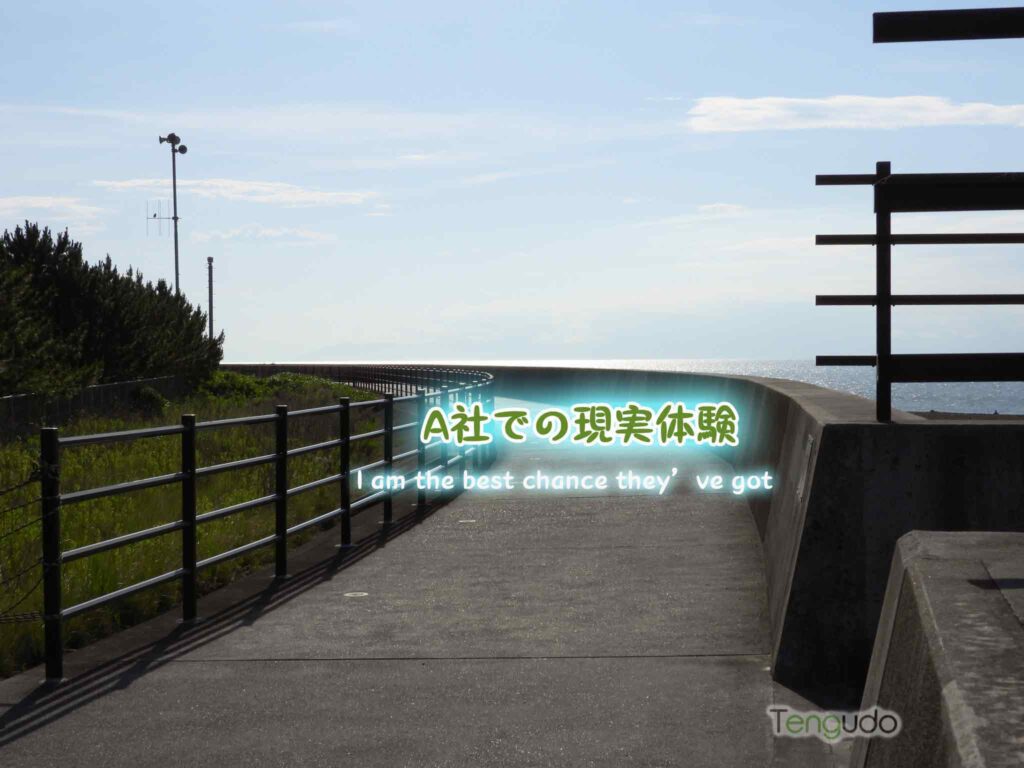部屋に入った瞬間、気が読めなかった。長い会議テーブルの両端には、日本のエンジニアと海外の営業チーム。設計ツールの画面が映し出されている。
わたしはその場にいたけれど――設計の経験も、CADの知識もゼロ。
「どうしよう、専門用語だらけだ…」
心臓が早鐘を打つ。眉間にしわが寄る。
そのとき、自分に言い聞かせた。
I am the best chance they’ve all got.
Don’t buckle.
Keep doing.
「現実」の壁
プレゼンが始まると、聞き慣れない言葉が矢継ぎ早に飛んでくる。
“parametric modeling”“workflow optimization”…
頭の中で「?」が連続する。
わたしは、声を失いかけた。でも、目の前の日本側の担当者がこちらを見ている。
わたしの訳出を待つ視線は、いつもと同じ「それで?何と言ったの?」。
I am the best chance they’ve all got.
Don’t buckle.
Keep doing.
深呼吸して、文脈から意味をつかみ、シンプルな言葉に置き換えて伝えた。
言葉よりも「温度」
会議中盤、日本側の担当者が静かに言った。「検討をお願いします。」
直訳しかできず Please review this request and make a proposal.
少し間を置いて、日本側のエンジニアが笑顔で言った。「マスターアグリーメント、ローカルアグリーメントがあるのはわかっていますが、詳細を詰める必要があるので。」
その訳出を聞いて海外チームの顔がふっと明るくなる。その瞬間わかった。
大事なのは関係を前に進める「温度」を正しく保つ。そのためのファクターXは存在する。そしてそれはわたしのような立場の人だけが届けられる。
止める勇気
議論が進むにつれ、略語も知らない言葉も乱れ飛んだ。
BOM、RFI…。
意味が食い違い始めたか、確認が入る。誰もが丁寧にひとつづつ確認して会議が進む。
わたしはプレッシャーを感じて、「どなたか質問ありませんか」と発言してしまった。
でも「No, we are fine so far」と返事があって、その後も、会議は中断前と同じペースで進み始めた。 あれは「止める勇気」だったのか?自分の正直な行動が場を救うこともある――初めて知った。
背中を押す言葉
何度も不安に押し潰されそうになった。「設計を知らない自分が、ここにいていいのだろうか。」
でも、そのたびに繰り返した。
I am the best chance they’ve all got.
Don’t buckle.
Keep doing.
商談成立、そして学び
数週間後、商談は成立した。それは成立するべくして成立した商談だったが、必要な要件は盛り込まれて双方ベストな形となった。わたしはどうやら、全員が安心して話せる場を支えたようだった。
あの日の経験が教えてくれたのは、通訳とは「言葉を変換する仕事」以上に、 会議の場に安心をつくる仕事だということ。
今でもわたしは、初めての通訳現場で心に刻んだ言葉を繰り返している。
I am the best chance they’ve all got.
Don’t buckle.
Keep doing.